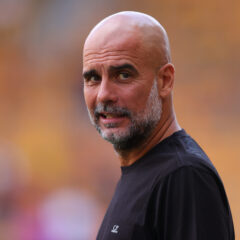欧州サッカー連盟(UEFA)が主催するCL、EL、ECLは、今季から大会方式が大きく変更された。CLを例にみると、昨季までは32チームが本戦に出場し、4チーム×8組によるグループステージが行われていた。グループ内でホーム&アウェイを行うので、各チームの最低試合数は6試合だった。
今季は出場チームが36に増加し、グループステージに変わってスイス方式のリーグフェーズが導入された。出場36チームをUEFAクラブランキングの順番に9チームずつ4つのポットに分け、各ポットから抽選で選ばれた2チーム×4ポット=8チームと対戦するというもの。すなわち、各チームが最低でも8試合を戦うことになったのである。
今季のCLの成績に応じた賞金は本戦出場で1862万ユーロ(約30億6110万円)、リーグフェーズでの勝利210万ユーロ(約3億4526万円)、引分け70万ユーロ(約1億1508万円)だった。勝ち上がることで賞金額は増えていくが、最低試合数が6→8に増えたことで各チームが成績による賞金を手にするチャンスが増えている。
これとは別に、UEFAが算出した係数をもとに各チームに支払われる分配金、TV放映権料などがある。分配金は最終順位が上位のほうが高くなるし、TV放映権料も試合数に応じて受け取れる金額が変わってくる。これまでより最低でもホームゲームが一試合多く、試合数の増加は間違いなく各チームの収益アップにつながっている。
試合数をなんとか増やしたいUEFAは、リーグフェーズのあとにラウンド16進出をかけたホーム&アウェイのプレイオフを設けることも忘れなかった。リーグフェーズの1位~8位はそのままラウンド16へ。9位~24位でプレイオフを行い、勝者がラウンド16進出というひと手間が加えられている。
すなわち、出場36チーム中、リーグフェーズで敗退するのは12チームだけ。残りの24チームは、少なくともCLを10試合は戦えるのである。
昨季までのレギュレーションだとラウンド16進出チームを決めるため、32チームによるグループステージで合計96試合が行われていた。新たなレギュレーションでは36チームがリーグフェーズで144試合+プレイオフ16試合=計160試合となっている。以前よりも64試合も多いのである。
前田大然、旗手怜央がプレイするセルティックはスコットランドでは強豪であり、CLに出場する常連クラブとなっている。ただ、この2年間はグループステージ敗退が続いていた。大会方式が変更された今季はリーグフェーズで3勝3分け2敗で21位となり、プレイオフに進出した。もし、16位までがそのままラウンド16にストレートインするレギュレーションであれば、ここで敗退していた。セルティックは新方式の恩恵を受けた形で、しかもプレイオフの相手はバイエルンだった。
結果としてバイエルンに敗れたが、第1戦が行われたホームのセルティック・パークは57,406人の観衆で埋まった。もともとホームには同程度の観衆を集めるが、こうした“ドル箱”とされるホームゲームが一試合でも増えるのはクラブにとってもサポーターにとってもうれしいことだ。セルティックは昨季までのレギュレーションだったら6試合で終わっていた可能性があったところ、10試合を戦うことができた。クラブは収入が増え、選手はハイレベルな経験をより多く積めた。こうした部分は、新方式によるメリットだったと考えられる。
![[特集/今季こそアーセナル! 03]充実スカッドの中でひときわ光る重要性 アーセナルをタイトルに導く6人](https://www.theworldmagazine.jp/wp-content/uploads/2025/11/1-3-240x240.jpg)
![[特集/今季こそアーセナル! 01]アーセナルが優勝するために 乗り越えるべき“3つの壁”](https://www.theworldmagazine.jp/wp-content/uploads/2025/11/ee94cccf33160ceea74ae3fc4c745e33-240x240.jpg)
![[特集/新生レアル徹底解剖 03]新たな戦力がアロンソ体制で台頭! レアルに新風を吹き込む若手5人](https://www.theworldmagazine.jp/wp-content/uploads/2025/10/050df8413e65a6ca3aae19ec31974723-240x240.jpg)
![[特集/新生レアル徹底解剖 02]連係良好で得点王へ一直線 機は熟した! 100%のムバッペがレアルで開花](https://www.theworldmagazine.jp/wp-content/uploads/2025/10/1b3d8f3b22f9095a8d1add43ebc8813d-240x240.jpg)
![[特集/新生レアル徹底解剖 01]王座奪還へ好スタート クラブを知るX・アロンソが挑むレアル変革](https://www.theworldmagazine.jp/wp-content/uploads/2025/10/31e010ea77d697ed6c0c3a9fb6841664-240x240.jpg)